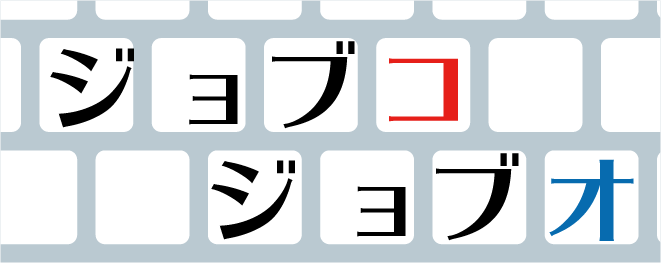接客業やサービス業などお客様と直接関わることの多い仕事をしていると、避けて通れないのがクレームです。
改善して欲しいという気持ちでクレームを入れるお客様から、時には理不尽な要求をしてくるお客様など、一言でクレームと言っても内容は様々です。
直接的な対応や電話対応でお客様が納得して頂けたら良いのですが、なかなか怒りが鎮まらないお客様も実際にいます。
このような場合は謝罪文を書き、改めて謝罪の気持ちを誠意を持って伝えることとなります。
しかし、書き方一つで謝罪の気持ちを台無しにしてしまうこともあるので、謝罪文を書く前には必ずポイントを理解してからにして下さい。
文字で伝えるからこそ、誤解を生まないように注意が必要です。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

-
書類の提出が遅れてしまった場合、社外へのお詫びメールについて
書類の提出を忘れていたり、作成が間に合わなかったりと、提出の遅れが生じた場合、先方にお詫びをしなくて...
-

-
クレームに対する謝罪方法、電話の相手へ共感を示しながら謝罪を
クレームの電話を受け取った時、こちらに非がなくてもまずは謝罪することが大切ですが、ひたすら「すみ...
スポンサーリンク
大変!お客様からクレームが入ってしまった!まずはクレーム対応の正しい手順について知ろう
クレームに対応するために王道と言われている手順があります。
実際にクレームが入ってしまうと、焦ってしまったり、怖くなってしまうと思いますが、この手順を覚えて、苦手意識を克服しましょう。
- お客様の心情を理解する
どのようなクレームの内容であっても、必ずクレームを入れる理由は存在します。
その理由を理解するためにも、お客様のお話をじっくりと伺うことです。
まず、自分が聞き役をすることよりも、話させ役をしていることに徹し、そのお話に共感しているということを示します。
お客様からのクレームを受け止めている事を伝えるには、あいづちやうなずき、復唱することが大事です。
お客様に対しての申し訳ない気持ちを伝えることを心がけます。
お話を伺う前に、一方的に謝ってしまうのは避けましょう。 - 事実を確認する
お客様のクレームの内容を伺った後は、解決策を提案するために、事実の確認を行います。
事実を正確に理解するためには重要なポイントです。
決してお客様を疑う様な言動はしないようにしましょう。 - 解決策や代替案を提示する
お客様は、クレーム先に対して、必ず謝罪や、解決することを求めます。
要望に応えることができない場合はその理由をしっかりと述べ、お客様の要望に対してどのように解決しようとするのか、もしくは、代替案を伝えることが大切です。 - お詫びと感謝
最後にお詫びをすることはもちろんですが、クレームに対して、今後の仕事をする上での貴重な意見を頂いたと感謝を伝えることも大切です。
クレームは会社の財産になるという考えを持つと、クレームに対処する際に大きな苦痛を伴わずに済むこともあります。
お客様からのクレームに謝罪文で対応する場合は、しっかりマナーを守ること
謝罪文ではお客様の表情が見えない分、しっかりと謝罪の気持ちが伝わる心を込めた文章でなくてはいけません。
謝罪文は、まず、電話での謝罪を行ってから出すようにしましょう。
謝罪文を作成する際は、手書きのものでもパソコンで作成するのもどちらでもかまいませんが、ビジネスマナーの沿ったものを作成するようにしましょう。
まず最初に宛名はしっかりと確認しましょう。
お客様のお名前の漢字、「様」が記入されているかなど。
差出人の名前も必ず記入しましょう。
差出人はクレーム内容によって変わります。
大きなトラブルがあった場合には代表者名で出すこともあります。
通常は、実際に接客した人や、クレームの際の電話に対応した人が多いです。
クレームに対する誠意を謝罪文で伝えるために、正しい書き方を理解しよう
それでは、どのように書くとお客様に誠意が伝わるのでしょうか。
謝罪文を正しく書くことによって、形だけの謝罪と思われないようにします。
もしも、実際には接客態度に問題が無くとも、お客様は必ず何かの原因があってクレームを言います。
その事実に対して必ずお詫びの言葉を入れるようにしましょう。
お詫びの言葉だけではなく、今後の対応策もしっかりと書くようにします。
また、お詫びの言葉は使い方に注意する事が重要です。
「ごめんなさい」「すみません」など、謝罪の言葉であっても丁寧ではありませんので、「誠に申し訳ございませんでした」や、「心よりお詫び申し上げます」などと書きましょう。
そして、お客様のクレームによって学ばせていただいたという感謝の気持ちを加えることで更に誠意が伝わります。
例えば、「今後のサービスに役立たせていただきます」や、「今後接客について誠意ある対応を徹底いたします」なとが良いでしょう。
共通しているのは、あて先となるお客様の名前をフルネームで、誤字、脱字のないようにしっかりと確認しましょう。
差出人の会社名、住所なども略したりせずに、正式名称で書くのがマナーです。
封書で送る際には、封筒の表書きはできる限り縦書きで、紙の折り方に気をつけましょう。
一方、メールで謝罪文を送る際には受け取った方がわかりやすい様に件名欄にお詫びについて送信したことがわかるようい明記した方が良いでしょう。
謝罪文の前に。お客様のクレームを電話で対応するときの心得
しかし、そのような態度はお客様に伝わってしまう時もあるのです。
お客様に不快を与えないためにも、電話での対応は重要です。
以下のポイントを心得ておくと、クレームを対応するときにスムーズに解決できるかもしれません。
まず、お客様のクレーム内容を聞き、お詫びや感謝の言葉、解決策の提案などはもちろんです。
もしも、電話を取るまでに少し時間がかかってしまった場合などは、お待たせしたことに対する謝罪をしましょう。
お客様が気持ちよく会話ができる雰囲気作りも必要です。
そんな時は、お客様の立場に自分を置き換えてみたりするのも1つの方法です。
クレームは自分自身を、もしくは商品を良い方向に導くための学びの機会だと思うことで、電話でのクレーム対応が円滑にいきます。
クレームを言うお客様の心理を考えれば、もっと適切な対応が出来るはず
クレームを言うお客様は、理由、原因、事情など様々です。
時にはご自身だけでは対応できないパターンも出てくると思います。
接客態度が悪かった、商品を間違えられたなどは、とにかく迅速に解決する事が重要です。
お客様の意見に共感した上でお詫びしましょう。
(先に来店したのに、後から来た人が先にサービスを受けたなど)
なぜ不平等に感じたのかを詳しく聞き、今後改善するにあたって役立てるように努力することを伝えましょう。
少しやっかいなのが、もともと機嫌の悪かったお客様が、ちょっとしたきっかけで不快に思い、クレームを言う時です。
こういうときこそ、話させ役に徹して、じっくりとお客様の気が済むまでクレームを聞きましょう。
度を越えたクレームだと感じた場合には即、第三者に相談しましょう。